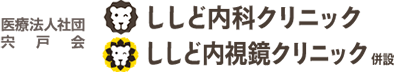便秘とは?症状の見分け方と受診の目安
 一般的に便秘とは、腸管が狭くなったり詰まったりして便が出にくくなり、排便回数も減り、便の水分量が減って硬くなる状態を指します。
一般的に便秘とは、腸管が狭くなったり詰まったりして便が出にくくなり、排便回数も減り、便の水分量が減って硬くなる状態を指します。
食事をしてから排便までの時間は、基本的には24時間程度ですが、その日の体調によっても変化します。しかし、2~3日に1回排便があり、不快な症状がなく、腹部の張りや不快感がなければ便秘とはみなされません。一方、毎日排便があっても、便の量が少なく、便が出しにくい場合や、便が出し切れていないと感じる場合は便秘とみなされます。
便秘は食物繊維の不足や運動不足が原因で起こることもありますが、治療が必要な病気の症状として現れている場合もあります。
また、便秘が長く続くと痔や大腸の病気にかかるリスクが高まります。慢性的な便秘は、痛みや日常生活での支障を引き起こすことがあります。便を出すのに力が必要になる、排便感が不完全、下痢と便秘を交互に繰り返す、便が出にくいなどの症状がある場合は、お気軽に当院へご相談ください。
便秘の原因
便秘の原因は様々ですが、大きく分けると「器質性便秘」と「機能性便秘」の2つに分類されます。機能性便秘はさらに「痙攣性便秘」「弛緩性便秘」「直腸性便秘」の3つに分類されます。
また、服用している薬の影響や、何らかの病気の影響で便秘になることもあります。
機能性便秘
弛緩性便秘
大腸の蠕動運動の低下によって起こる便秘です。腸管の緊張が緩んで蠕動運動が抑制され、便がうまく運べず大腸内に長時間留まってしまいます。時間が経つと便から水分が吸収されるため、ますます便が出にくくなります。
腹筋力の低下やダイエット、食物繊維や水分の摂取不足、運動不足などが原因と考えられ、女性に多く見られるとされています。
また、食欲不振、残便感(腸内に便が残っている感じ)、腹部膨満感(お腹が張って苦しい)などの症状が見られ、肌荒れ、イライラ、肩こりなどを引き起こすこともあります。
痙攣性便秘
過度な緊張が大腸にかかることによって起こる便秘です。自律神経の乱れにより副交感神経の働きが過剰になり、自律神経によって調整されている腸管に過度な緊張がかかり、便が小さく丸いウサギの糞のような形状になります。排便しようとしても少量しか出ず、下腹部に痛みを感じたり、残便感が見られたりします。下痢と便秘を交互に繰り返すことに加え、環境の変化やストレスが自律神経のバランスを崩し、病気を引き起こすこともあります。交代型や便秘型の過敏性腸症候群も、痙攣性便秘に分類されます。
直腸性便秘
直腸に便が溜まることで起こる便秘です。便が直腸まで運ばれてくると便意を感じ、通常は排便の最適なタイミングとなります。しかし便意を感じても便を我慢してしまうことが続くと、便が直腸まで運ばれてきても排便反射が起こらず、便意を感じなくなり、直腸に便が溜まっていきます。そして溜まっている便が原因で排便が困難になる場合もあります。加齢によって起こりやすくなると言われますが、痔によって便意を我慢しがちになることでも起こります。
器質性便秘
直腸瘤や腸管の癒着、大腸がん、腸閉塞(イレウス)などによって、大腸や小腸の通り道が塞がれてしまう便秘です。このタイプの便秘の場合、下剤の服用には注意が必要です。下剤の服用により腸に穴が開く「腸穿孔」という危険な状態を引き起こす可能性があるためです。器質性便秘は治療が必要な病気ですので、嘔吐や激しい腹痛、便に血が混ざるなどの症状がある場合は、早めに当院へご相談ください。
便秘を伴う疾患
 便秘を放置すると、大腸内の便がますます硬くなり、排便がさらに困難になります。
便秘を放置すると、大腸内の便がますます硬くなり、排便がさらに困難になります。
また、便を無理に出そうとしたり、便が硬くなったりすると、痔になりやすくなります。
痔を発症すると排便時の出血や激痛が起こりやすくなり、排便を避けることで便秘が慢性化してさらに排便が困難になります。
特に外痔核(切れ痔)の場合は、便秘によって病状が悪化し、症状を繰り返すことで傷跡が残って肛門が狭くなり、排便がさらに困難になることもあります。
最悪の場合は、排便ができなくなり手術が必要になることもあります。
また、内痔核(いぼ痔)の場合、無理に便を出そうとすると、痔核の悪化に繋がります。
さらに、内痔核がある場合、便秘のときに無理に便を出そうとすると、痔核が肛門の外に飛び出して出血することがあります。病状が悪化すると直腸粘膜が肛門から脱出することもあります。
また便が硬くなり太くなると肛門で詰まることがあり、外から便をかき出すための対策を講じないと排便できず、硬い便の間に下痢のような便が出ることもあります。
さらに、慢性的な便秘は虚血性大腸炎、腹膜炎、大腸穿孔、潰瘍性病変などにも繋がります。これらは全て、早急な治療が必要となる深刻な病気です。便秘の原因は上記以外にも、様々な病気や症状、問題が原因で起こることがあります。
便秘の検査と診断
問診では、これまでの病歴や特に困っている症状、これまでの症状の変化、便通や便秘の状況などを詳しく伺います。 そして、便秘の原因やパターン、便秘の原因となっている病気がないかなどを考えながら、腹部のレントゲン検査、腹部の触診や聴診などを行い、現在の状態を確認した上で診断します。 さらに詳しい検査が必要な場合は、大腸カメラ検査、血液検査、腹部超音波検査、CT検査などの追加検査を行います。大腸カメラ検査は、病気による腸管の閉塞や狭窄の有無を確認できます。また、腸管の長さを確認したり、それぞれの病気特有の異常の有無を確認したり、組織を採取して確定診断を行うこともできます。ポリープや早期がんも、主に大腸カメラ検査で発見が可能です。当院では、検査経験豊富な内視鏡専門医による、丁寧かつ正確な検査を心がけています。鎮静剤を使用することで、苦痛なく検査をお受けいただけます。
便秘の治療
便秘が何らかの病気によって起こっている場合は、その病気を治療することが必要です。腸管自体に何ら異常が見られない場合は、薬物療法や生活改善によって治療を行います。
薬物療法

下剤には様々な種類があり、下剤以外にも、便の水分量を調整するなど様々な効果を持つ薬があります。
その他にも漢方薬を併用したり、新しい作用機序の薬を開発したりと、多様な選択肢があります。当院では、患者様の生活スタイルや便秘のパターンを考慮しながら薬を処方し、定期的に病状を確認しながらきめ細かく調整していきます。
生活習慣の見直し
便秘の改善だけでなく、再発を予防するためには、運動習慣や食生活など生活習慣を見直すことが大切です。また、適切な排便習慣を整えるためにも、便意を感じたら我慢せず排便することを心がけましょう。
当院では、患者様の負担をできるだけ軽減しつつ、効果的な生活習慣の改善をサポートします。どんな小さなお悩みでもお気軽に当院へご相談ください。効果的な改善方法を一緒に考えていきます。